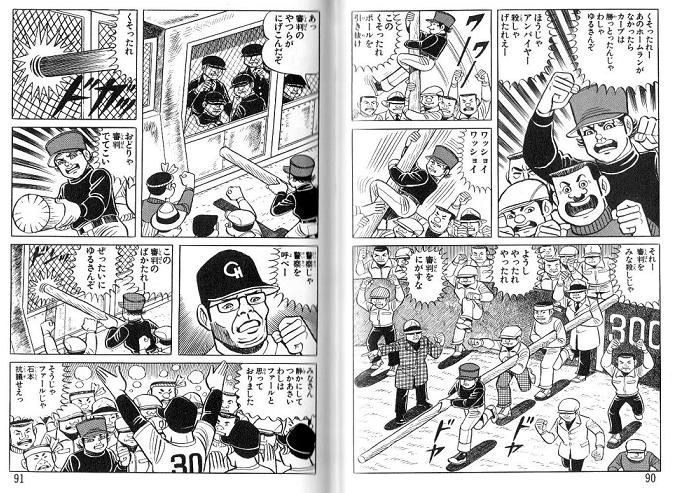今夜、横浜DeNAベイスターズが広島東洋カープを破り、3位から、しかも首位カープと14.5ゲーム差というシーズンでは大差を付けられた状態からの日本シリーズ出場を決めた。
きっとスポーツニュースや新聞、さまざまなメディアでCSというものについて議論が活溌になるだろう。やれ10ゲーム差付いたらアドバンテージを2にせよ、そもそもCSは要らん、いっそ地域ごとにリーグ再編せよ、だの。
ワタクシ個人としては幼少からのホークスファンであり、最近では昔ほど熱心に見てはいないが、それでも気になるチームではある。
そんなわけで、このブログでも旧プレーオフやCSで敗退することについて度々取り上げてきた。
今年もイーグルス相手にあわや、という状態だったようだし、下手したら3位同士の日本シリーズもあり得たわけで、そうなったらそうなったで面白かったかもしれない。
結論を言えば、CSは現行制度のままでよい。そう思っている。
変わらなければならないのは、CSのルールではなくファンやメディアだろうと、むしろ感じている。
長い長いシーズンを戦い抜くために必要なものと、5試合制、あるいは7試合制といった短期決戦に求められるものは必然的に大きく異る。それを忘れてはいけない。
CSや日本シリーズは短期決戦だ。そして、オリンピックやWBCといった国際大会もまた、明々白々に短期決戦なのである。
戦後以来のプロ野球。そろそろファンもメディアも、真剣に、短期決戦をどう克服し、勝ち抜くかについて意識を高めていかなければならない。
WBCこそ第1回第2回と連覇を果たしたが、オリンピックを含めて日本代表・侍ジャパンは短期決戦には決して強くないと感じている。むしろ、しおしおなことのほうが多かったような気がする。
なぜか。
それは、監督コーチ陣はもちろん、選手もファンもメディアも、短期決戦をきちんと研究してこなかったからだ。ワシが育てた愛着ある選手と心中しようとしたり、妙な「型」にこだわって勝利の方程式だとかなんとか。
だから、過去日本球界には名将と呼ばれた人は数多いが、日本シリーズで強いと呼ばれた監督となると、数えるほどしかいなくなる。特に投手陣の分業制が確立されたここ数十年では、さらに絞られる。
短期決戦では要所要所で臨機応変な用兵をしなければ勝ち抜くことは難しい。以前、WBCについて書いたときの繰り返しになるが、クローザーよりも重視すべきはストッパーであったり、相手との相性はもちろんベンチ入り選手の好不調をきちんと見極めた上でのスタメンなど、思考停止でなくきちんと考えて闘いに臨む姿勢がないと、良い成績を収めることは難しいだろう。
そういった意味では、今年パ・リーグのCSをどうにか勝ち抜いたホークスの工藤監督はちょっとだけ見直した。連敗スタートしたことで危機感を高めたのだろうが、城所の使い方など用兵の臨機応変さについては、少なくともバッティングオーダーでは発揮されていた。
投手起用でもジョーカー嘉弥真の使い方は上手いなと思ったが、8回9回を固定しちゃうあたり、まだまだである。反面、梨田監督は良い面も多かったが、策を弄しすぎた感のほうが強かったかな。
今年のカープのCSについては、鈴木誠也やエルドレッドを欠いていたこともあり、不運な面も確かにあった。冒頭にも書いたように、関係者やファンは本当にどん底であろう。ホークスを応援していた私には、その気持が本当によくわかる。
だが東京オリンピックで野球が復活するいま、日本球界が世界大会で好成績を収めるためにも、短期決戦の楽しみ方、批判の仕方、頭の弱い解説者の皆さんにもそのへんの意識をきちんと持ってもらって、全体的なレベルを上げる必要があると思っている。
だからこそ改めて言おう。CS制度は変える必要がない。変わるべきは、他にあるのだと。