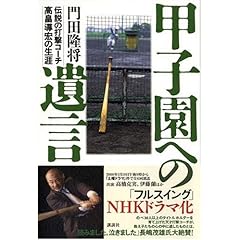こどもの頃、紙幣の肖像が切り替わったとき、夏目漱石や福沢諭吉は知ってるけど「新渡戸稲造」って誰? とは多くの人が思ったのではなかろうか。
十和田に行ったついで……と言ってはナニだが、町外れにある「新渡戸記念館」にも足を伸ばしてみた。


知らなかった。十和田市とは、新渡戸稲造の祖父・新渡戸傳(にとべつとう)という人が開拓した町だったのね。もともと茶屋が数件しかなかった三本木原と呼ばれていたエリアに、灌漑用水として稲生川を作るわけなんだけど、その土木工事がすさまじい。完成したのは1859年。お江戸の時代に約4年の歳月をかけて、人工河川を作ったのだ。
新渡戸傳は南部盛岡藩にいたんだけど、藩が与えてくれた予算だけでは足りず、私財まで投じたとか。それで新渡戸家は、十和田市民にとっては特別な存在なんだそうだ。
以上、新渡戸記念館の資料のパクりです。記念館自体は、こじんまりとした佇まいだったけれど、新渡戸ファミリーの歴史はもちろん、十和田市ができるまでのこと、そしてもちろん稲造コーナーも充実しており、なかなかの見応えですぞ。イサム・ノグチの手による、新渡戸稲造のレリーフなんかもあった。
新渡戸稲造は、「BUSHIDO」を書いた人として有名だよね。さすがにオイラもそれくらいは知っていた。でも、読んだことはないんですよ。英語で出版されて世界中でベストセラーになったそうだけど、外国人の学者に「キリスト教のような宗教がなかったら、どのように道徳を教えられるのか」と問われたのが執筆のきっかけだったらしい。
それで思い出したのが、関川夏央+谷口ジローの名著、「坊ちゃんの時代」シリーズの第二巻、「秋の舞姫」。この中で、ドイツ留学中の鴎外森林太郎がナウマン象で有名なナウマン博士に食って掛かるシーンがある。ちょっと長くなるけど、抜粋させて頂く。
「日本は急速な西欧化を目論んでおる。その意気やよし、知識欲やよし。しかし残念ながら日本は西欧化近代化の基礎となるべきキリスト教文化を欠いておる。(中略)わたしは断言する、日本が西欧と肩を並べる日はついに来たらず」と語るナウマン。さらには日本人を猿にたとえ、その努力によって優秀な猿にはなれるだろうが、とうてい人間たり得ないとするナウマンに対して、鴎外がキレる。
「日本には古来、武士道があります。武士道は信と義との結晶です。道徳(モラル)です。ゆえにクリスチャニティを必要としません。(中略)我々は、数千年心性を鍛えぬき、いま西欧の覇道から身を避けるためにたかが数百年の洋智を学んでいるのです」
さらには日本人はよく恥辱を忍ばない、前言の訂正なくば決闘を、と迫り、ついにはナウマンに謝罪させる。
おそらくこの場面は関川夏央による脚色ではなかろうか。実際に、鴎外とナウマンがドイツの新聞紙上で論争を繰り広げたという史実は、ちょこっとググるといくつか出てくる。
だが、実際に鴎外が噛み付いたナウマンの発言としては、「仏教は女性を認めていない」的なニュアンスに対してであり、鴎外が武士道を引き合いに、ゆえに日本はクリスチャニティを必要とせず、としたという内容は見つからなかった。
あくまでも個人的な想像だけれど、関川夏央は新渡戸稲造とBUSHIDOのエッセンスを、鴎外に落とし込んだのではなかろうか。奇しくも、森林太郎も新渡戸稲造も1862年生まれであり、同じく1884年に海外へと留学している。なんたる偶然。とはいえ、当時の両青年の気概に共通したものがあったことは想像に難くない。
なお、鴎外は「舞姫」にあるようにエリスとは破局したが、新渡戸稲造はアメリカ人のクェーカー教徒であるメリー夫人(日本名は萬里)を娶った。
長くなったついでに、「坊ちゃんの時代」シリーズでは重要な位置を占める「大逆事件」について、新渡戸稲造にも面白いエピソードがあるのね。
徳富蘆花という人がいて、この人は「不如帰」を書いたりしたんだけど(ついでに言うと、京王線の芦花公園駅は、徳富蘆花の旧邸だったりもする)、1910年の大逆事件後、旧制第一高等学校にて「謀叛論」と題した講演を行い、多いに天下国家を批判。学生たちの喝采を浴びた。じつはその場所を提供したのが、当時一高の校長だった新渡戸稲造。
このことが当局に問題視され、なんと新渡戸稲造は一高の校長をクビになってしまうのですね。大逆事件については、明治の知識階級に計り知れない衝撃を与えたというけど、おそらく新渡戸稲造も、あまりにもあからさまな判決(無関係な人も含めて24人に死刑宣告)に対して批判的だったのでしょうなあ。
大いに脱線しまくりですが、ちょっとBUSHIDOを読んでみなくてはなあ、と思った次第。とりあえず、新渡戸記念館で軽めの解説書を購入したけれど。
いやはやそれにしても、明治人は本当にすごいよ……。









 ガムをどうぞ(byマサ)
ガムをどうぞ(byマサ)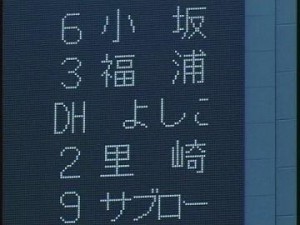 代打よしこ
代打よしこ