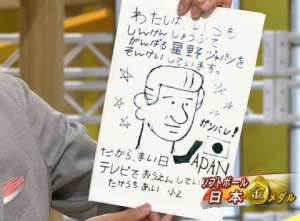音楽とかをガンガン入れるわけでもないので32でいいかとも思ったのだが、手元にあるコンテンツの総量をひとしきり考えたところ、最悪の事態とは、それを管理するのがメンドくさくなることだと気づいた。そんで64である。アホだ。
3Gはどうするか最後まで迷ったのだが、ソフトバンクでSIM Lockだなんてどうよ? ということで却下。どうせ今年はiPhoneも機種変することになるので、通信系はそっちでいいだろう。
さて、あとは手塚治虫全集を「自炊」して……と。誰かやってくんないかなあ!

ところで手塚治虫といえば「火の鳥」。中でも「太陽編」が好き。火の鳥というシリーズ自体、古代と未来を振り子のようにして現代へと紡がれているわけだけど、太陽編は作品自体が壬申の乱の時代と21世紀を行き来している。
物語は白村江の戦いに始まって、壬申の乱自体を、日本古来の八百万の神vs大陸からやってきた仏教、という形になぞらえるあたり、スケールも大きく、非常に読み応えがあります。
いっぽうで近未来と設定された世界では「光」という宗教が世界を支配しており、それに与しない人々は「シャドー」として地下に暮らしている。ゴキブリの唐揚げなんかを日常的に食べたり。
まあ、物語の解説はどうでもいいんですが、その近未来で、主人公は「光」による理不尽な支配状態を打破すべく、その総本山に乗り込み、テロを行うんですよねえ。
私は最近のAppleのことを考えるとき、よくこの「火の鳥・太陽編」のことを思い出します。
おっと、Appleがマーケットにおいて支配者的存在になり、すっかりevilと化したとか、そんな話にしたいわけではありません(笑)。
ただまあ、世の中全体という大きな枠も、あるいは数人による小さなコミュニティーでも、支配構造の変革というのは常に起きりうるんだけど、ざっと歴史を見渡すと、意外と人間って同じことを繰り返すようになっとるのですね。
弱くて虐げられた者が、大きな力を持つ者に立ち向かい、勝利を手にする。そこにカタルシスは生まれ、大抵の物語はそこでハッピーエンドを迎える。
平凡なフィクションの世界でなら、それでもいいでしょう。しかし、現実世界では物語はとどまることなく続くわけで。あ、もちろん火の鳥・太陽編は、凡百のごとき終わり方ではなく、そのあたりキッチリと描かれています。
つくづく、火の鳥シリーズは完結してもらいたかった……。