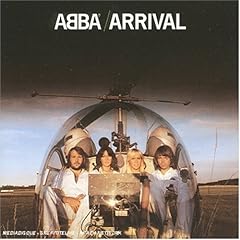個人のblogとはいえ、誰が見てるんだか分からないところにこんなこと書くのもアレですが……。
サンフランシスコのオファレルSt.に、ミッチェルブラザーズというストリップ劇場がある。正確には、Mitchell Brothers O’Farrell Theatreというんだけど、私に近しい人であれば、その話を聞いたことがあるかもしれない。大絶賛していたはずだが、おそらくは伝えたいことの10%くらいしか言葉に表せていなかったのではないかと思う。
言い訳するわけではないが、殊更ストリップ鑑賞が好きなわけじゃあない。とはいえ健康な男子なのでそれなりに興味もあって、学生時代に数回ほど行ったことがあるのは事実。浅草と、あとは水上。浅草ロック座なんかは、独特の風情がありますね。ついに足を踏み入れることはなかったが、渋谷の道頓堀劇場なんかも、できれば行っておきたかった。
水上温泉での体験はひどかった。客が我々の団体(といっても3人くらいだったかな)しかおらず、半ばヤケクソで、半ば仕方がなく「かぶりつき」の席に座り、義務的に見入るハメに。冬の鄙びた温泉街の、あのどんよりと重苦しい隠微な雰囲気は、それはそれで面白いものがあったけれど。
こうした後ろ暗さ(?)があるからか、はじめてアメリカでストリップ劇場に行ったとき、衝撃を受けたのだ。これはすごいな、と。

早朝、サンフランシスコの公園にて。本文とは関係ありませんw
よくある話だけど、最初は仕事関係の仲間たちと酔った勢いで。確か全日空ホテル(いまは違うホテルになってるかな)の前でタクシーに乗り、運ちゃんに「ストリップに行きたいんだけど?」の一言で連れていってもらった。
後日、そこはポルノ界のパイオニアと呼ばれる、伝説のミッチェル兄弟が作った劇場だと知ることになる。日本人が連想するストリップとはまったく異なる(言い方は妙だが)、健全で、明るくて、ユーモアに溢れていて……とにかく感動の一語だったのですね。店も客も、とにかくノリがいい。だからなのか、女性客もチラホラいたくらい(ていうか、じつは私の連れにも女性の同僚がいたんですが)。
劇場内は、メインとなるステージ(左右にお約束のポールが立っていて、いわゆるストリップが入れ替わり立ち替わり)があって、それ以外にも色んな部屋があるのね。のぞき系とか、ポルノ映画を延々流してるシアターとか、おねいさんが膝の上に乗ってくれる部屋とかw
でも一番ウケたのが、「コペンハーゲン・ラウンジ」っていう名前がついた部屋で、ここはガランとした真っ暗な空間のみ。んで部屋に入ると、椅子の上に懐中電灯型のスポットライトが置いてある。中央では女の子が2〜3人ウネウネしていて、客はそれを照らして……という感じ。
なんか、そう書くとすごくエッチっぽく思うかもだけど、客の反応が「グフフ……」みたいなのじゃないんですよ。むしろ「俺たち、なんてアホなことしてるんだ!ガハハ!」「そんな立派なナリしてるくせして、自分がやってることを冷静になって見てみろ!」「オマエモナー!」「(一同)ゲラゲラ」みたいな、妙な連帯感が醸し出されてて最高に面白かった。部屋の名前からして、ノリのよさがあるよね。
はたして、アメリカのストリップ劇場がすべてあんな感じなのかは分からない。単に自分が行ったときが「当たり」だっただけなのかも。少なくとも、ダークでウェットな感じは微塵もなかったのは確かだ。
てなことを、サンフランシスコに詳しい某ジャーナリスト(その筋では非常にカタブツで有名な方)に話をしたら、「そのストリップ劇場は超有名で、映画にもなってるんだよ。そんなに気に入ったならDVDでも買えば?」とおっしゃる。
その映画こそが、『キング・オブ・ポルノ(原題は”Rated X”)』だ。しかもミッチェル兄弟の弟を演じてるのは、チャーリー・シーン。プラトーンとかメジャーリーグの彼ですね。兄役は、エミリオ・エステベス。よく似てるって、リアルで兄弟だから当たり前か。
もちろんDVDは購入。なのに、見るタイミングを逸したまま行方不明になっていたのが、最近になってカイシャの段ボールの片隅に押し込まれてたのを発見したのです。
あー、いつものことですが前フリが長い……。それをとうとう見ることができたと、そーいうエントリーなわけでございます。ちょっとダメポな部下に付き合って、朝まで仕事しなくちゃならなくなり、その合間に鑑賞。
いやー、題材が題材ではあるんだけど、これがなかなか面白い。
ミッチェル兄弟は、ラディカルな父親(実際はプロのギャンブラーだったらしい)に育てられます。兄は大学で映画製作を学んだりするんだけど、折しもベトナム戦争。西海岸といえばお花が満開なフリーダム・ムードが蔓延していて、なぜかポルノ映画を作ることに。で、いつの間にか弟も巻き込んで、さらには理解ある両親にも支えられ、自前の映画館がほしいってんで”Mitchell Brothers O’Farrell Theatre”を作っちゃう。全米で大ヒットした”Behind the Green Door”という作品を生み出し、大金持ちにまで上り詰める。サクセ〜ス!
NYでマフィアが海賊版で勝手に上映していると聞けば、FBIに手を回して、マフィア相手の争いにも堂々勝利。アメリカで販売されているビデオなんかでは、本編前に必ずFBIによる著作権関係のWARNINGが入りますが、そもそものきっかけが、ミッチェル兄弟の映画があまりにも人気で海賊版が上映されまくってたのを取り締まるためだったそうで。へぇ。
70年代から80年代へと時が移り、世の中に家庭用ビデオなんてものが普及し始めるとポルノ映画は斜陽化していきます。そこでシアターを改造して、ストリップやショーを売り物にした、という歴史があるんですね。なお、ポルノ映画を作ってた最後の頃には、駆け出し時代のトレーシー・ローズ(その後、超有名なビデオ女優になる)も出演していたそうだ。なるほど、ポルノ界のパイオニアだねぇ。
実話をベースとした映画ではあるけど、ドキュメント風なわけではなく、とにかくそのぶっ飛んだ生き様を追うだけでも楽しい。題材は確かにポルノなんで、それっぽいシーンもいくつか出てくるものの、そんなにエッチな感じではないかな。むしろ兄弟モノなんで。
古くはカインとアベルとか、ポピュラーなテーマだけど、この映画の場合、どっちもダメ人間というのがユニーク。それゆえか、とても切ない。毛色は違うけど、シド・アンド・ナンシー的な空気もちょこっと感じたり。
映画自体、特にお勧めとかではありません。私のように、実際にMitchell Brothers O’Farrell Theatreに行ったことがある人ならば、話のタネにはなりますが。とはいえ予備知識ナシで見てみたいという奇特な方のために、特にwikiなどにはリンクは張っておりません。兄弟の壮絶な生涯、そして運命は有名な話らしく、割とサラッとネタバレしてるところが多いんで。
日本映画界でも、ポルノ出身の名監督って多いよね。何度も書いてるけど、おくりびとの滝田カントクとか。ほとばしる才能はまず、矛先をエロスに向けるのかもしれないねぇ。本作でも、いくつかポルノを撮影してるシーンが出てきますが、設定とかムチャクチャ。セックスシーンさえあれば、あとはナニやってもOKみたいな、むしろそういった状況で作品として仕上げるのって、やっぱ才能なんだろうなー。AVなんかが出回る前の、古き良き時代ということなのでしょう。
ついでについでに、ミッチェル兄弟の弟の息子が柔術家になってて、日本でも総合格闘技の大会に出てるんですよ。ググってたら偶然見つけたんだけど、カレブ・ミッチェルといって、グレーシー柔術系だとか。
あー、仕事終わんねー。朝までの予定がもう昼過ぎじゃねーか!おかげで駄長文に……。