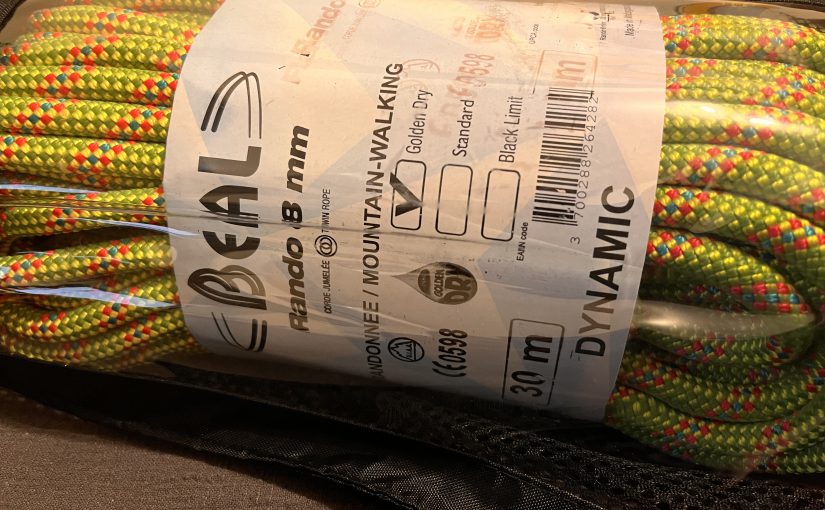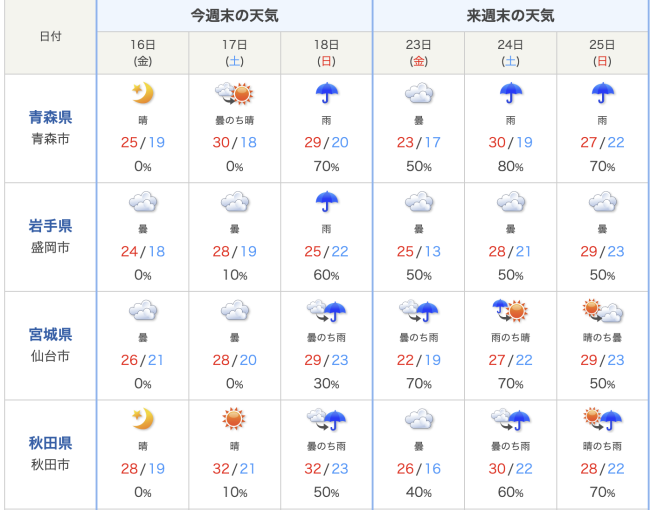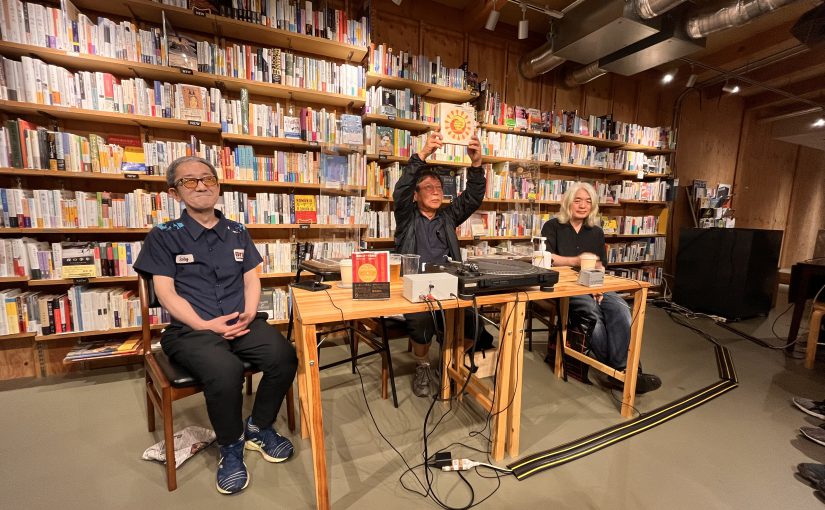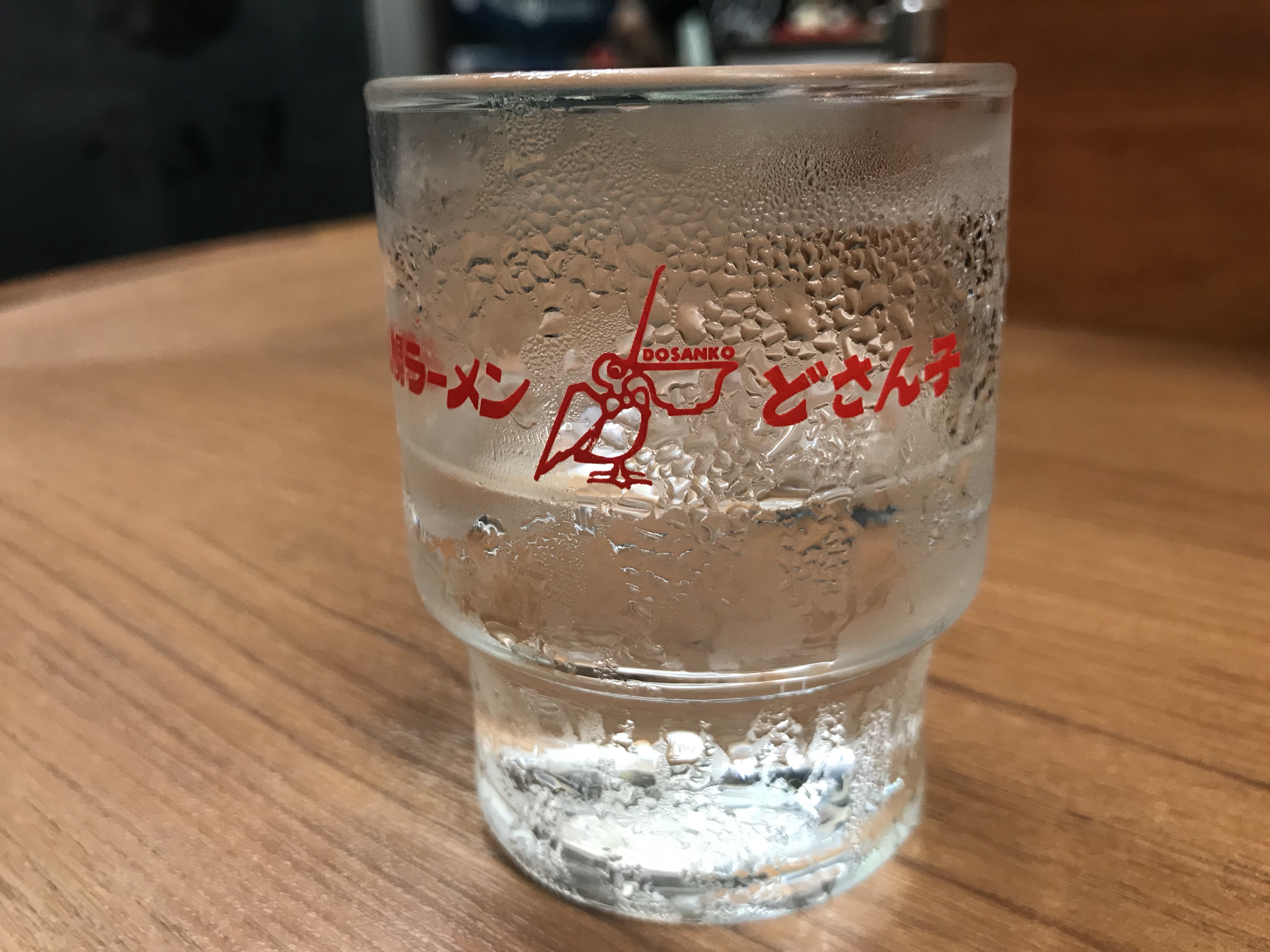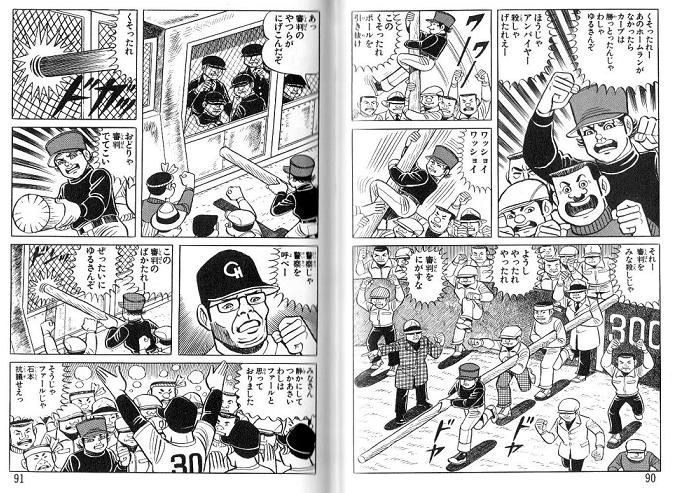ここ数年、地元クラブのジュビロ磐田を中心にJリーグを見ている。今期はJ1昇格を果たし、出だしこそまずまずだったが気がつけば最下位に定着。残り5試合となったところで、J1残留に向けていよいよ正念場……というか、ほどほどに絶望感が出るくらいには不利な状況となっている。
思えばシーズン前、昨年のチーム得点王のルキアンが福岡に移籍したところでイヤーな空気があったし、そこには近年エレベータークラブと揶揄され続けた福岡の、J1残留に対する執念がビンビンに感じられた。
要は、単なる補強に留まらず(残留争いの)ライバルチームのエースを抜くことによる弱体化により相対的な戦力格差を生み出すという、まさに福岡にとっては一石二鳥となる戦略である。現時点で福岡は残留争いでも上位におり、悔しいことではあるがその妙手がピタッとハマった展開となっている。
今年は関東の行ける範囲でアウェイのジュビロ戦を中心に観戦を重ねてきた。
浦和 4-1 磐田
川崎 1-1 磐田
東京 2-0 磐田とはいえ3試合か。1分け2敗の観戦成績。
浦和戦は試合以上に雨に祟られたんだよなー。しかも傘忘れてズブ濡れで美園まで歩いた。埼玉スタジアムは初だったけれど、やっぱり大規模な専用スタジアムっていいよなー。あと浦和サポは声出してなくても「圧」がすごかった。隣のオッサンのボヤキ解説に辟易とした。
等々力までは自転車で行った。行きは汗だく、帰りは真っ暗で怖かった。大久保の引退イベントが楽しかった。
味スタはまあ、勝手知ったるご近所。
コロナ規制もあっていずれも声出しはNGだったが、サッカーは現場で見るのが面白い。JFLとかも見に行っちゃいそうだ(味スタの横でやってるんだよね)。
さて。
いまの磐田を見ていると、組織づくりとはかくも難しいものかと思い知らされる。
いったん負の連鎖に陥ったときの立て直し、つまるところのリスク管理が現場任せだとこうなるよなーという典型である。結局、ろくな補強をすることもできないままシーズン終盤を迎えているわけで、ホームの観客動員が寂しいのは、単に強くないだけでなく、サポーターだってそのへんを理解しているからだ。
かつては黄金期を築いたってのも含めて、懐かしの南海ホークスと同じかぐわしさで、個人的には馴染み深いのだが、若いサポならたまったもんじゃないよね。
藤田がSDとして復帰してきたけれど、今期の結果がどうであれ、若手中心のチーム構成に切り替えてほしいなあ。古川、藤原、あと後藤とか素材はいっぱいいるわけで、彼らが海外に見つかっちゃう前に土台を構築していただければと思う。